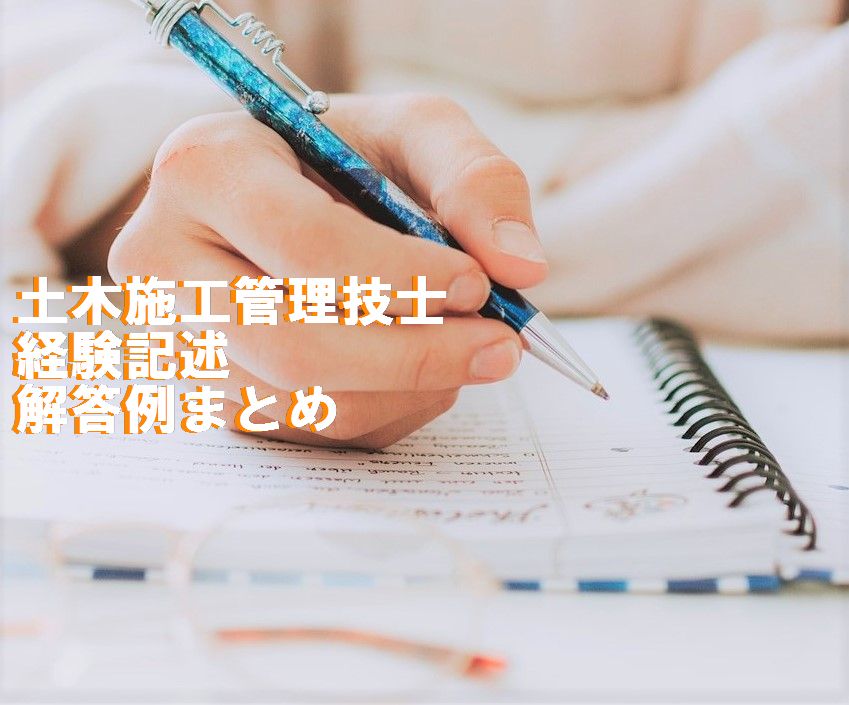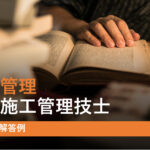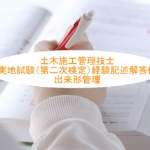※この記事はプロモーションを含みます。
土木施工管理技士の実地試験(第二次検定)には経験記述を書く項目があります。
経験記述を書くことは、合格への必須条件であり、さけては通れない問題です。(書かないとそれだけで不合格)
そんなこと言っても、どう勉強したら良いか分からないという方も多いですよね。

自分の経験した工事をどうまとめよう…
参考になる作文例や解答例があればいいな…
こんなお悩みを解決します。
そんなわけで、この記事では土木施工管理技士の経験記述の例文(解答例)を公開しています。
それではさっそく参りましょう。ラインナップはこちら!
二級・一級土木施工管理技士・経験記述の例文・作文例の種類
経験記述は、
- 安全管理
- 品質管理
- 工程管理
- 出来形管理
- 施工計画
- 環境対策(保全)
- 建設副産物
のうち指定されたものについて、自分の経験した工事で記述します。
ただ近年10年ほどは、1級・2級どちらも【安全管理】、【品質管理】、【工程管理】が出題される傾向にあります。
ニ級&一級土木施工管理技士の経験記述!安全管理の例文・作文例
1級土木と2級土木では、行数が異なるので注意してください。
2級土木よりも1級土木のほうが、より具体的な内容を書くことを求められています。
土木施工管理技士・安全管理の経験記述例文➀
まず初めに、工事概要や現場状況・懸念事項、技術的課題について記載します。
解答例)
本工事は、〇〇県〇〇市〇〇市内にある△△トンネル手前に歩道を設置する道路改良工事であった。
工事箇所は1車線規制による施工であったため、作業場所は十分なスペースを確保することができなかった。
また、工事はのり面を掘削し、擁壁コンクリートを打設しなければならないため、狭小現場での作業員と建設機械との接触による事故が懸念された。
従って、作業中の作業員と建設機械との接触を防止することが重要な課題であった。
土木施工管理技士・安全管理の経験記述例文②
検討した項目と検討理由及び検討内容を記載します。
解答例)
現場内での接触防止のため、次の事項を検討した。
①毎日が連続の同作業であるため、慣れ不注意による事故をぼうしするための対策について検討した。
②ダンプトラックからの盛土の積み下ろしの際、バックホウと作業員との接触を防止するため、立ち入り禁止範囲を定め、進入を防止するための対策について検討した。
③ダンプトラックでの搬入、搬出は連続して行われ、また現場内への進入は後進運転だったため、作業員との接触事故の防止と安全な誘導を行うための誘導員の配置について検討した。
土木施工管理技士・安全管理の経験記述例文③
技術的課題に対して現場で実施した対応処置を記載します。
解答例)
上記の検討結果に基づいて、本工事では下記の対応処置を実施した。
①毎日のKYKにおいて、作業員に安全チェックリストの確認及び安全対策への目標を書くことを義務化し、安全確認の周知徹底及び意識向上を図った。
②バックホウの旋回範囲をカラーコーンで囲い、立ち入り禁止範囲を明確にし、旋回作業の際は監視員を配置して作業を実施した。
③ダンプトラックの搬入・搬出の際は誘導員を配置し、安全な誘導を行った。
これらの対応処置により、無事故で工事を完成・終了させることができた。
安全管理の書き方についてもっとくわしく知りたいかたは以下の記事を参考にしてください。
-

-
2級土木の経験記述例文・安全管理!書き方や出題形式のポイントまとめ
続きを見る
ニ級&一級土木施工管理技士の経験記述!品質管理の例文・作文例
解答例に加え、具体的な現場や周囲状況を追加し、オリジナリティを意識しましょう。
土木施工管理技士・品質管理の経験記述例文➀
まず初めに、工事概要や現場状況・懸念事項、技術的課題について記載します。
解答例)
本工事は、〇〇県〇〇市〇〇町内を流れる一級河川〇〇川の上流に設置された砂防堰堤につづく流路工事であった。
工事時期は〇月~△月の冬期であったため、帯工でのコンクリートが寒中コンクリートになることが判明していた。
さらに1月~2月の過去の気象データからは、日平均気温が4℃以下となる日は延べ30日程度、最低気温は-9°程度であった。
従って、冬季におけるコンクリートの初期養生により、凍害を防止して所定の強度を確保することが重要な課題であった。
土木施工管理技士・品質管理の経験記述例文②
検討した項目と検討理由及び検討内容を記載します。
解答例)
寒中コンクリートの対策として次の検討を行った。
①コンクリートの運搬による温度低下、移動によるタイムロスを防ぐため、現場から1番近いプラントを選定し、骨材・水の過熱について検討した。
②初期養生の温度低下を防ぐため、シート養生の方法について、すきま風及び内部の熱漏れを防ぐため、特にシートの重ね合わせ部について検討した。
③所定の圧縮強度を確保するため、給熱養生について検討した。
④コンクリート打設後の温度低下を防ぐため、打ち込み時の時間帯について検討した。
土木施工管理技士・品質管理の経験記述例文③
品質例文3:技術的課題に対して現場で実施した対応処置
解答例)
上記の検討結果について、本工事では以下の処置を行った。
①現場から一番近いプラントを選定し、運搬時間◇分、骨材及び水は加熱したものを使用し打ち込み温度を△℃~〇℃とした。
②シート養生はラップジョイントとし、重ね幅は〇cmとし、さらに粘着テープによる目張りを行った。
③現場に練炭を設置し、内部温度5℃以上を保ち、◇日間の養生を行った。
④コンクリート打ち込み時間帯はその日の気温に合わせて日中〇℃以上ある暖かいときのみに限定した。
上記の結果、初期養生による凍害を防止して、所定の強度■N/mm²を確保することができた。
品質管理の解答例についてもっとくわしく知りたいかたは以下の記事を参考にしてください。
-

-
1級土木経験記述の例文「品質管理」を紹介!最新の出題形式変更に対応
続きを見る
ニ級&一級土木施工管理技士の経験記述!工程管理の例文・作文例
続いては工程管理です。
土木施工管理技士・工程管理の経験記述例文➀
まず初めに、工事概要や現場状況・懸念事項、技術的課題について記載します。
解答例)
本工事は○○年〇月に発生した台風○○号及び○○豪雨により一級河川○○川が増水し、堤防が崩壊したため崩壊部に盛土を行い、間知ブロック張工を施工する災害復旧工事であった。
工期半ば、8月の初旬に、河川の増水による締切盛土の崩壊が発生し、工事中止等によって20日の工程遅れが生じた。
一方で発注者との協議により、工期の延長はできないことが判明していた。
従って、残工期◆ヵ月間で、施工量アップによって工期内に工事を完成させることが重要な課題であった。
土木施工管理技士・工程管理の経験記述例文②
技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容を記載します。
解答例)
残工事において、20日の工程短縮を図るため、次の検討を行った。
①ネットワーク式工程表に基づいて、8月中旬段階での工程フォローアップを実施した結果、間知ブロック張工がクリティカルパスであることが判明した。
従って、日施工量をアップするための施工管理について他工種との関連性も含めて検討を行った。
②夜間照明等を準備して、1日2時間程度の残業による施工量確保について検討した。
③施工業者から提案されていたブロック納入業者は1社であったが、日施工量アップに見合う納入能力がないため、もう1社追加する方向で発注者と協議し指示を行った。
④現在の機械編成では、特に細かな駄目処理がネックとなって日施工量アップの障害となるため、追加投入すべき機種について検討を行った。
②については、労働規定の範囲内で1日2時間程度の残業について検討を行ったが、夜間での作業は危険を伴うため、この検討内容については実施を見合わせた。
土木施工管理技士・工程管理の経験記述例文③
技術的課題に対して現場で実施した対応処置を記載します。
解答例)
以上の検討結果について、本工事では下記の処置を行った。
①工程のフォローアップ結果から、間知ブロック張の施工を2工区に分割することとし、施工班を1班追加投入し、作業員を○名増やしたことで約△日間の工程短縮ができた。
②発注者と協議を行い、間知ブロックの納入業者を1社から2社に変更し、日納入数量を確保した。
③バックホウ1台、移動式クレーン1台の機械編成にクレーン仕様のバックホウ1台を追加し、駄目処理でのロスタイムを大幅に低減した。
上記の対応処置を実施した結果、工期内に工事を完成させることができた。
工程管理の解答例についてよりくわしく知りたいかたは以下の記事を参考にしてください。
-

-
工程管理の経験記述の作文は?1級&2級土木施工管理技士実地試験解答例&例文あり
続きを見る
ニ級&一級土木施工管理技士の経験記述!出来形管理の例文・作文例
出来形は、品質管理の一種ですが、より具体的な基準値などが求められます。
土木施工管理技士・出来形管理の経験記述例文➀
まず初めに、工事概要や現場状況・懸念事項、技術的課題について記載します。
解答例)
本工事は、交通量の比較的多い幅員7mの国道の歩道部に、延長260mの汚染管を布設し、マンホール工及び取出し工を施工する下水道工事であった。
近くには、1級河川○○川が流れており、現場周辺は扇状地に位置するため、粘性土地盤が広く分布し、地下水位も比較的高い地域であった。
従って、地盤の不同沈下が予想され、非常に緩やかな管路設計勾配の3パーミルを全延長にわたって確保すること、9基あるマンホールの基準高さを設計どおり確保することが大きな課題であった。
土木施工管理技士・出来形管理の経験記述例文②
検討した項目と検討理由及び検討内容を記載します。
解答例)
管路勾配と、マンホールの基準高確保のため、次の事項について検討した。
①丁張間隔は、当初10mに1カ所を予定していたが、VU管の定尺長■mを基準にして△m間隔とし、管の先端と後端での高さ確認も併用することを検討した。
②管路の砂基礎の材料は設計で山砂になっていたが、当地区の山砂はシルト分が多いため、良質な川砂への変更を検討した。
③マンホール位置での試掘の結果、3基に相当する箇所が、1m程度の軟弱層を挟んでいることが判明した。安定処理、置き換え、丸太杭基礎について対比し、最適な工法選定について発注者と協議を行うこととした。
④マンホール底版の基準高の規格値は設計値±30mmであるが、多少の沈下を打ち消すため、プラス側の社内管理基準の採用を検討した。
上記において、軟弱層対策は工法の比較検討の結果、施工性・経済性等から1.5mの松丸太4本による杭基礎を提案することとし、他の対策と併せて実施を決定した。
土木施工管理技士・出来形管理の経験記述例文③
技術的課題に対して現場で実施した対応処置を記載します。
解答例)
以上の検討結果について、本工事においては次のような対応処置を実施した。
①丁張を■m間隔に設置し、この位置での水糸からの下がり検測、管長4m毎の管両端のレベルによる高さ確認を実施した。
②発注者との協議の上、砂基礎の使用材料を山砂から川砂に変更し、締固めを入念に行った。
③発注者の承諾を得て、マンホールの基礎を松丸太杭とし、底版の基準高を0~+△mmで管理した。
これらの処置により、設置管路勾配及びマンホール底版の基準高(設計値+○~+■mm)を確保し、所定の出来形とすることができた。
出来形管理の解答例についてよりくわしく知りたいかたは以下の記事を参考にしてください。
-

-
経験記述【出来形管理】1級土木&2級土木施工管理技士の実地試験対策
続きを見る
ニ級&一級土木施工管理技士の経験記述!施工計画の例文・作文例
計画段階での内容を具体的に書きましょう。
土木施工管理技士・施工計画の経験記述例文➀
まず初めに、工事概要や現場状況・懸念事項、技術的課題について記載します。
解答例)
本工事は、県道をアンダーパスする村道用に、幅3.5m、高さ4.5m、長さ21.0mの場所打ちボックスカルバート2基を設置する工事であった。
現場は山間部に位置し、資材運搬路として使用する村道は、現場近くで幅員が狭くなる箇所があり、アジテータトラックがコンクリート打設場所に接近できない状態であった。
また、舗装端部の破損により、大型車の通行が危険な箇所が3カ所点在した。
従って、ボックスカルバートに関するコンクリートの打設方法と大型車の通行を確保する仮復旧の検討が、施工計画立案にあたって重要な課題となった。
土木施工管理技士・施工計画の経験記述例文②
検討した項目と検討理由及び検討内容を記載します。
解答例)
コンクリートの打設及び舗装破損部の仮復旧の計画立案に際し、次の検討を行った。
①現場条件を勘案して、クレーンを用いたバケットによる打設法とコンクリートポンプを用いた圧送による打設法について可能性を検討した。
②現場近くに、資材の積み替え等に使用する移動式クレーンやアジテータトラック、コンクリートポンプ車が配置可能な場所が確保できるか検討した。
対象範囲としては、コンクリートの圧送可能な水平距離で概ね300mを目安とした。
③舗装端部破損により大型車通行が危険な場所については、舗装による路肩復旧とH鋼打ち込みによる路肩補強について検討した。
上記検討項目のうち、打設方法については、バケット方式ではクレーンの作業半径が大きくなり、打設能力が低下することから、ポンプ圧送方式を採用することとして、No15付近の平場を切り広げてスペースを確保することとした。
また、路肩の補強については、再度破損地点の法面の状況などについて、目視確認を行うこととした。
土木施工管理技士・施工計画の経験記述例文③
技術的課題に対して現場で実施した対応処置を記載します。
解答例)
以上の検討結果について、本工事においては次のような施工計画とした。
①No15付近の平場を切り広げてスペースを確保し、アジテータトラックとポンプ車の2台を乗り入れ、ここから水平距離250m、垂直距離20mを圧送する計画とした。
②スペースの広さはこの他に移動式クレーンが同時に配置できる広さで計画した。
③舗装端部破損個所の3地点を再調査したところ、舗装端から法肩までは1.0m~1.4mの距離があり、法肩の崩壊や法面の亀裂・損傷はなく、舗装表層の破損と判断されたので、加熱アスファルト混合物による仮復旧で対処する計画とした。
上記の施工計画を実施した結果、工期内に工事を完成させることができた。
施工計画の解答例についてよりくわしく知りたいかたは以下の記事を参考にしてください。
-

-
経験記述の施工計画とは?土木施工管理技士の実地試験対策(解答例付き)
続きを見る
ニ級&一級土木施工管理技士の経験記述!環境保全の例文・作文例
環境対策では、現場状況に合わせた対策や管理が大切です。
土木施工管理技士・環境保全の経験記述例文➀
まず初めに、工事概要や現場状況・懸念事項、技術的課題について記載します。
解答例)
本工事は、河川堤防に存置された既設コンクリート構造物である樋管を撤去した後に、堤防を復旧させる工事であった。
河川に二重締切を設け、仮設堤防を施工した後に、掘削、既設構造物撤去、復旧を行う工事であるが、工期が約10か月と長く、堤防に近接して民家が散在していた。
また、工事用車両は、比較的民家が連なっている町道を通行しなければならなかった。
従って、建設機械による騒音・振動の抑制、工事車両による粉塵の発生防止等、周辺住民に対する環境保全が重要な課題であった。
土木施工管理技士・環境保全の経験記述例文②
検討した項目と検討理由及び検討内容を記載します。
解答例)
周辺住民に対する環境保全として、本工事においては次の検討を行った。
(1)近接民家に対する騒音・振動の抑制対策としては、
①騒音の拡散を抑えるたきめの仮囲いの種類・設置方法について、
②矢板打ち込み・引き抜きに使用する機種の選定について、
③コンクリート構造物の取り壊し方法、特に使用する重機について、
④特定建設作業に関わる作業時おうほ間帯について、各々具体的な内容の検討を進めた。
(2)工事用車両による町道での粉塵発生の防止対策としては、
①車両のタイヤに付着した泥を現場内で除去する方法について、
②強風の日や乾燥した日の町道の清掃の実施について、具体的な内容の検討を行った。
仮囲いは、12㏈程度の騒音遮断効果のある防音シートを採用し、タイヤ洗浄機はより効果の大きな湿式洗浄機を選定した。
これらを含めて上記の検討内容を実施することを決定した。
土木施工管理技士・環境保全の経験記述例文③
技術的課題に対して現場で実施した対応処置を記載します。
解答例)
以上の検討結果について、本工事においては次のような対応処置を実施した。
①防音シートを提内に向け3方向に設置した。
②矢板工では、低振動型機種である油圧式高周波打ち込み・引き抜き機を使用した。
③樋管の取りこわしは、大型ブレーカの単独作業から圧砕機との併用に変更した。
④特定建設作業は9時から17時とし、土・日曜日は休止した。
⑤タイヤ洗浄機を設置し、作業員による強風時などの町道清掃も実施した。
上記の処置を実施した結果、騒音では62㏈前後、振動では57㏈前後にまで大きさを抑えることができた。
また、粉塵に対する周辺住民からの苦情もなく、工事を完成させることができた。
環境対策(保全)の解答例について、もっと知りたいかたは以下の記事を参考にしてください。
-

-
土木施工管理技士の経験記述「環境保全」を公開!1級&2級土木実地例文あり
続きを見る
ニ級&一級土木施工管理技士の経験記述!建設副産物の例文・作文例
建設副産物の再利用や、できるだけ出さない処置を記述しましょう。
土木施工管理技士・建設副産物の経験記述例文➀
まず初めに、工事概要や現場状況・懸念事項、技術的課題について記載します。
解答例)
本工事は、市街地を通る片側2車線の国道において、劣化等で損傷を受けている舗装表層を切削し、排水性混合物でオーバーレイを行う修繕工事であった。
表層切削工において、約1,000トンの切削廃材が発生するが、現場に近い中間処理施設は廃材保管場所がせまかった。
また他工事から大量のコンクリートがらを受け入れているために、この施設の使用は難しく、40km以上はなれた遠隔の施設に搬入せざるを得なかった。
従って、現場近くでの切削廃材の有効活用を図ることと、他の建設副産物の適性な処理が本工事における重要な課題であった。
土木施工管理技士・建設副産物の経験記述例文②
検討した項目と検討理由及び検討内容を記載します。
解答例)
切削廃材の有効活用と他の建設副産物の適性処理のため、以下の検討を行った。
①切削廃材の処理について発注者と協議を行い、周辺の地方自治体から活用の可能性について、情報を集めることとした。
②切削廃材の再利用事例に関する過去の実績を整理して、地方自治体への説明資料の作成を検討した。
③打換え工では、既設舗装版及び下層路盤の一部を撤去するが、舗装版と粒状路盤材の分別方法を検討した。
④50mの側溝入換え工があるが、既設鉄筋コンクリート側溝の処理について、分別解体方法をどうするのか、対応を検討した。
上記検討事項のうち、切削廃材については、現場に隣接する○○町から利用方法について説明してほしいとの情報があり、具体的な協議を進めることとした。
切削廃材の再利用事例集は、本社の技術部門に依頼して作成した。
また、現場事務所の敷地を利用して資材置き場を設け、コンクリートがら等の前処理を行うことを決定した。
土木施工管理技士・建設副産物の経験記述例文③
技術的課題に対して現場で実施した対応処置を記載します。
解答例)
以上の検討結果について、本工事においては次のような対応処置を実施した。
①廃材は、○○町の町民広場の表面処理材として、再利用することで合意した。
覚え書きを交わした後、管理簿によって搬出数量等を確認しながら、廃材の運搬・敷き均しを行った。
②舗装版と粒状路盤材は分別して積み込み、舗装版については資材置き場で小割専用圧砕機による小割を行い、中間処理施設に搬出した。
③既設側溝は、資材置き場において圧砕機で小割して、コンクリートがらと鉄筋を分別した後に搬出した。
この結果、廃材処理の再利用が図られ、他の建設副産物も適正に処理することができた。
建設副産物の解答例についてもっとくわしく知りたいかたは以下の記事を参考にしてください。
-

-
建設副産物の解答例!1級&2級土木施工管理技士の経験記述例文を公開
続きを見る
記述例文の丸写しは本試験では失格となりますので、あくまで参考にしてくださいね。
また、経験記述には工事名や発注者名などを書く共通部分があります。
10分くらいの動画でサクッと解説していますので、ぜひご覧ください。
👷受講者52,000名以上の実績👷
ニ級&一級土木施工管理技士の経験記述!作文例・解答例を参考に書いてみたけど不安な方へ
でもやっぱり独学で経験記述を書くのは不安だという方には、経験記述をプロが代行・添削してくれるサービスがあります。(独学サポート事務局)
だれかに添削してもらうと、安心して試験に臨めますよ。
独学サポート事務局の口コミやサービス内容についてはこちらの記事をどうぞ。
続きを見る
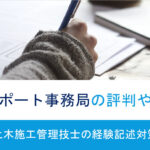
独学サポート事務局の口コミや評判は?作文代行あり・施工管理技士
![]()
![]()
※経験記述の添削や作成サービス
一方、わたしもココナラで、1級&2級土木施工管理技士の添削や作成のサービスやってます。
購入前にメッセージでぜひご相談ください。
経験記述添削サービス!土木施工管理技士合格できます 1級&2級土木施工管理技士の経験記述を添削します
【無料】まだココナラを登録してない方は以下のリンクから登録できますよ 😉
ココナラ公式サイト>>簡単!無料会員登録はこちら
今回は以上です。
参考になればうれしいです。
ありがとうございました。
この記事を書いている人

- 元公務員の土木ブロガー
- 1級土木施工管理技士、危険物取扱者乙4、玉掛などの資格あり
- 某県庁の土木職として7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 公務員土木職の仕事内容や、土木施工管理技士の資格に合格するための勉強方法などをブログで情報発信しています。
- ココナラで土木施工管理技士★経験記述の添削や作成サービスもやってます。
それではさっそく参りましょう。ラインナップはこちら!