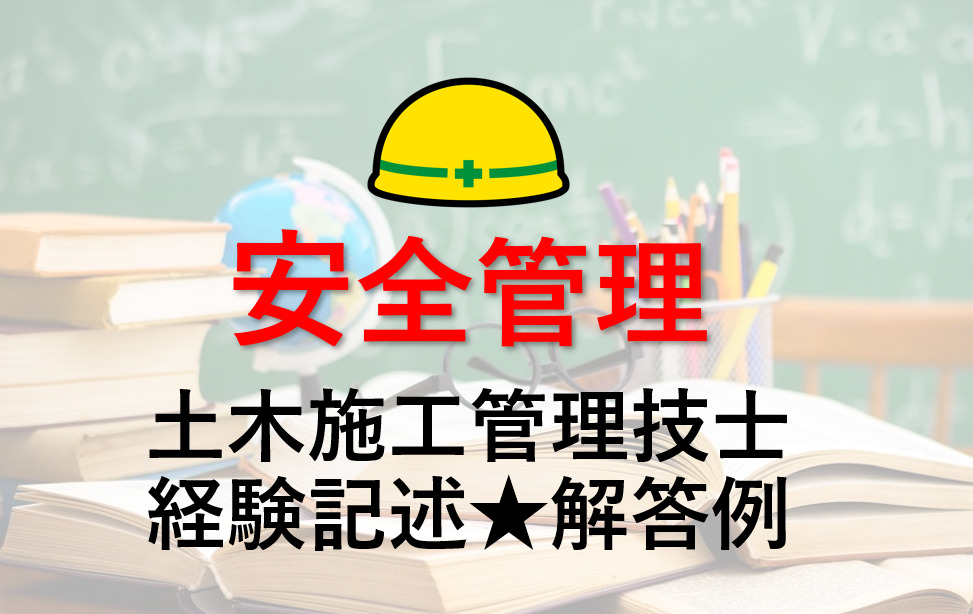2級土木の経験記述は、実地試験で必須問題となっているため、さけては通れない問題です。
この記事は、「自分の経験した工事をどうまとめよう…」と悩んでいるあなたのお悩みを解決します。
今回のテーマは【安全管理】の経験記述です。(作文例あり)
2級土木について、安全管理の経験記述に関する例文やポイントをまとめました。
2級土木の経験記述例文!安全管理編
2級土木施工管理技士の経験記述(安全管理)の例文について見ていきましょう。
2級土木経験記述の工事概要の例文
今回は【安全管理】での経験記述例を公開します。
設問1では、自分が経験した工事の基本的な情報を書くことになります。
本番では何も見てはいけないので、しっかり暗記して書けるようにしておきましょう。
(1)工事名
道路改良工事 国道○○号その6(快安道補)
(2)工事現場における施工管理上のあなたの立場
現場代理人or工事主任or発注者側現場監督員など
※立場については、旧受験資格か新受験資格かで名称が変わるので、手引きを必ずご確認ください。
(3)工事内容
- 発注者名:〇〇県○○土木事務所整備第二課
- 工事場所:××県△△郡○○町○○地内
- 工期:令和元年9月29日~令和2年2月10日
- 主な工種:舗装工、擁壁工
- 施工量:舗装(種類、厚み)工A=1500㎡、擁壁コンクリート打設量V=800㎥
現場の状況が分かるようによりくわしく書けるとよいです。
2級土木の経験記述!安全管理の例文・作文例
2024年から、経験記述の出題形式が変わり、質問が変化するようになりました。
ちなみに令和6年度に出題されたテーマは品質管理と工程管理でした。
そして令和6年の過去問での質問内容は以下のとおり。
〔設問1〕工事概要に記述した工事の「品質管理」に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。
(1)具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題
(2)(1)で記述した技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置
-------------------------
〔設問2〕工事概要に記述した工事の「工程管理」に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。
(1)施工条件や現場状況の観点から、工程管理上、留意した事項(工事着手前、工事中のいずれでも可)
(2)(1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由
今回は、設問1の品質管理を安全管理に置き換えて例文を書いてみます。
【質問内容】
〔設問1〕工事概要に記述した工事の「安全管理」に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。
(1)具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題(7行)
安全管理例文➀
本工事は道路脇にコンクリート擁壁を設置し、国道〇号の道路上での舗装を行う
工事であった。現場は片側通行による施工であり、またカーブが多く見通しの
悪い箇所であったため、一般車両から工事箇所が見えづらい状況であった。
さらに道路の沿道には住宅や店舗が立ち並んでおり、十分な作業スペースが
確保できないため、建設機械と作業員との事故も想定された。
このため、一般車両の安全確保と、建設機械と作業員の接触事故防止が
安全管理上の技術的課題となった。
(2)(1)で記述した技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置(7行)
安全管理例文②
技術的課題を解決するため、一般車両からの視認性を高める工事区画の明確化と
工事看板の工夫について検討した。この検討に対する対応処置としては、工事区画
のバリケードにLEDランプを取付け、工事看板は蛍光色を選び、起終点〇m手前から
配置した。また建設機械と作業員の接触事故を防ぐため、施工機械への対策と作業員
の服装について検討した。この検討に対する対応処置としては、タイヤローラにバック
モニターを取付け、死角を極力減らした。また作業員には目立つ色の安全ベストを
着用させたことにより、無事故・無災害で工事は完成した。
ただし、2024年以降の出題形式の変更により、丸写しができなくなりました。
質問はあくまで一例であり、毎年変わる可能性が高いです。
2級土木の経験記述「安全管理」を書く時のポイント!安全に関する例文
第二次検定における安全管理の経験記述のポイントは、
「現場においての予測される危険性とその防止対策について重点をおいているか」
ということが大切です。
現場での災害の発生が予測される状況や作業に着目します。
そしてその防止対策としてとられている不安全な状態を取り除くための措置と、工事従事者に不安全な行動をとらせないための処置について、注意して確認する必要があります。
ここでいう災害の発生とは、以下のような状況が考えられます。
| 安全の具体例 | 例文 |
| 飛来・落下物 | 高所からの工具落下を防ぐ対策 |
| 交通事故 | 一般車両と作業員の事故(視認性の向上、周知方法など) |
| 地山の崩壊 | 土留め支保工の倒壊、地山崩壊を防ぐ法面の処置 |
| クレーンの転倒事故 | クレーンが転倒しない地盤対策 |
| 酸素欠乏 | 作業員の酸素欠乏を防ぐための処置 |
これらの不安全な状態を取り除くための措置について記述し、不安全な行動をとらせないための措置(ミーティングや安全教育など)を考えて対応していることがわかるような文章を心がけましょう。
例文を参考に2級土木の経験記述を書いたら添削を受けよう
土木施工管理技士の経験記述については独学で合格する人もたまにいますが、かなり稀です。
基本的には土木施工管理技士の合格者や、添削のプロにに見てもらうことをおすすめします。
まずは例文を参考に自分なりに書いてみて、添削してもらいましょう。
自分では気づけなかった点を指摘してもらえると思います。
一方、別テーマの経験記述・解答例などについては別記事でくわしく書いていますのでそちらをご覧ください。
また、


そんな人には、土木施工管理技士の経験記述を作文代行(添削)してくれるサービス【独学サポート事務局】があります。
一方、添削だけなら、ココナラ ![]() で土木施工管理技士の添削や作成サービスがあります。
で土木施工管理技士の添削や作成サービスがあります。
私個人も添削サービスを実施していますので、興味のある方はぜひ確認してみてください。(購入前にメッセージでご連絡ください)

土木施工管理技士の経験記述ていねいに添削します 1級&2級土木施工管理技士経験記述の添削サービス
2級土木経験記述の例文・安全管理まとめ!
2級土木経験記述(安全管理)の例文についてお届けしました。
安全管理の経験記述まとめ
- 作文例や例文を見ながら自分の工事をまとめてみる
- 例文を参考に経験記述が書けたら添削を受けよう
- 安全管理の経験記述ポイントは、現場の予測される危険性とその防止対策について重点をおいて文章書くこと
出題形式が変わり、2級土木の第二次検定試験もかなり難易度が上がっています。
経験記述については例文を参考に書いてみて、必ず添削のプロに見てもらうのが合格の近道です。
試験がんばってください!(^^)!
この記事を書いている人

- 元公務員(土木職)の土木ブロガー
- 1級土木施工管理技士、危険物取扱者乙4、玉掛などの資格もち
- 某県庁の公務員土木職として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 今はブログで土木施工管理技士や土木知識などをメインにさまざまな情報を発信しています。