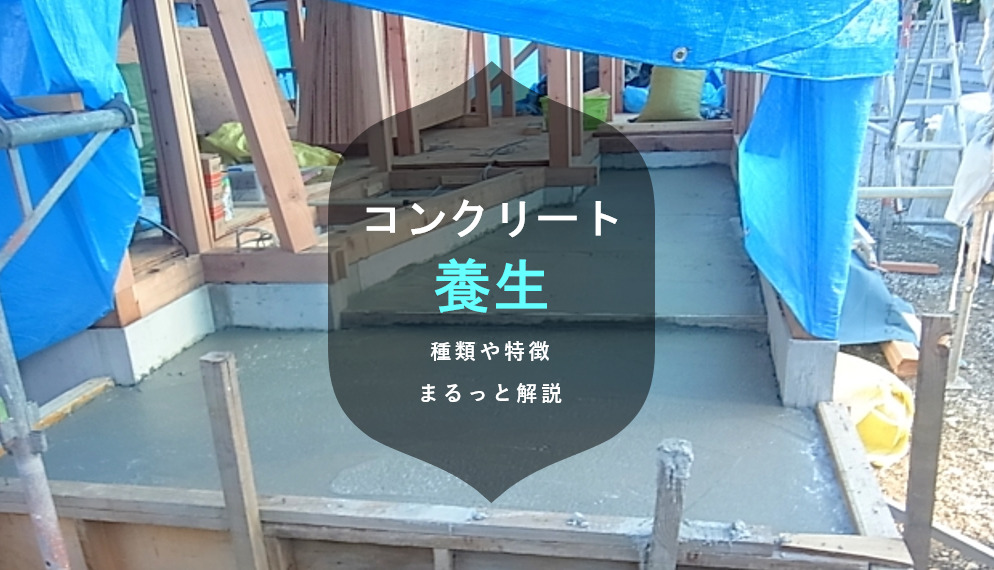コンクリートの養生は、打ち込み後に硬化し強度が増すまで、コンクリートを保護する大切な役割があります。
また、養生の種類はさまざまで、養生期間などの標準も定められています。
土木や建築などでは必須となる知識です。
それぞれの目的や種類をサクッとみていきましょう。
コンクリート養生方法の種類や養生期間
コンクリート養生方法を分類すると以下のこんな感じです。
| コンクリート養生 | ||
| 湿潤養生(湿潤に保つ) | 水中養生(標準養生) | |
| 湛水養生 | ||
| 散水養生 | ||
| 湿布(養生マット、むしろ) | ||
| 湿砂 | ||
| 膜養生 | 油脂系(溶剤型、乳剤型) | |
| 樹脂系(溶剤型、乳剤型) | ||
| 温度制御養生(温度を制御する) | マスコンクリート | 湛水、パイプクーリング |
| 寒中コンクリート | 断熱、給熱、蒸気、電熱など | |
| 暑中コンクリート | 散水、日覆いなど | |
| 促進養生(工場製品) | 蒸気、給熱など | |
| 有害な作用に対し保護する養生 | 常圧蒸気養生 | |

コンクリート湿潤養生(湿潤に保つ養生期間も)

| 湿潤養生
(湿潤に保つ) |
水中養生(標準養生) | コンクリートの強度試験用供試体のテストピースを20±3℃に保った水中、または湿度100%に近い湿潤状態で行う方法
空気中で養生するよりも温度変化が小さく精度が高い |
|
| 湛水養生 | コンクリートの表面に数cmの水を張って養生する | ||
| 散水養生 | コンクリート表面に水を撒く(スプリンクラーなどを使用) | ||
| 湿布(養生マット、シート) | マットやシートなどで覆い、水分の蒸発を防ぐ | ||
| 湿砂 | 湿った砂でコンクリート表面を覆い、乾燥を防ぐ | ||
| 膜養生 | コンクリート表面に膜養生材を散布して被膜を形成し水分の蒸発を防ぐようにした養生 | 油脂系(溶剤型、乳剤型) | |
| 樹脂系(溶剤型、乳剤型) | |||
コンクリートは打ち込み後、硬化を始めるまで、日光の直射や風などによる水分の散逸を防がなくてはなりません。
また、コンクリート打ち込み後ごく早い時期に表面が乾燥して内部の水分が失われると、セメントの水和反応が十分に行われず、また急激に乾燥するとひび割れの原因になります。
表面を乱さず作業ができるほど効果したのち、コンクリートの露出面は養生マット、布などを濡らしたもので覆うか、散水または湛水を行い、湿潤状態に保ちましょう。
一方、湿潤養生期間の標準日数は以下のとおり。
| 日平均気温 | 普通ポルトランドセメント | 混合セメントB種 | 早強ポルトランドセメント |
| 15℃以上 | 5日 | 7日 | 3日 |
| 10℃以上 | 7日 | 9日 | 4日 |
| 5℃以上 | 9日 | 12日 | 5日 |
さらにせき板が乾燥するおそれのあるときは、散水し湿潤状態に保ってください。
膜養生を行う場合には、十分な膜養生剤を適切な時期に、均一に散布しましょう。
そして膜養生は、コンクリート表面の水光りが消えた直後に行うことがポイントです。
養生に加え、コンクリート打設時間や注意点も確認しておくと良いでしょう。
コンクリート温度制御養生(温度を制御する)
|
温度制御養生 (温度を制御する) |
マスコンクリート | 大塊状に施工される質量や体積の大きいコンクリート
厚さ80~100cm以上、下端が拘束された壁では厚さ50cm以上のコンクリート(コンクリート標準示方書) |
湛水、パイプクーリング |
| 寒中コンクリート | 日平均気温が4℃以下 | 断熱、給熱、蒸気、電熱など | |
| 暑中コンクリート | 日平均気温が25℃を超えるとき | 散水、日覆いなど | |
| 促進養生(工場製品) | コンクリートの凝結・硬化、強度発現を促進するためにコンクリートを加熱する養生方法 | 蒸気、給熱など |
コンクリートは、十分な硬化が進むまで、硬化に必要な温度条件を保ち、低温、高温、急激な温度変化などによる有害な影響を受けないよう、必要に応じて温度制御養生を行います。
マスコンクリートは温度応力によるひび割れが発生するおそれがあるため、表面保温やパイプクリーニングなどにより、コンクリート温度や温度差を制御しなければいけません。
また外気温が高い場合には、セメントの水和反応が促進される影響も加わるので注意しましょう。

外気温が著しく低い場合には、セメントの水和反応が阻害され、強度発現が遅れたり、初期凍害を受けたりするおそれがありますのでご注意ください。
そのため、日平均気温が4℃以下になる場合には、寒中コンクリートとして扱う必要があります。
反対に、外気温が著しく高い場合、コンクリート表面も乾燥しやすくなりひび割れを生じる可能性も高くなります。

よって日平均気温が25℃を超えるときには、暑中コンクリートとして対応しましょう。
寒中コンクリートおよび暑中コンクリートについてもそれぞれ対策方法が異なるので注意が必要です。
一方、工場製品の養生では、練り混ぜたあとに2~3時間以上経過してから蒸気養生を行うと定められています。
有害な作用に対し保護するコンクリート養生
| 有害な作用に対し保護する養生 | 常圧蒸気養生 | 高温度の水蒸気の中で行う促進養生のことで、大気圧下で行う養生 |
有害な作用とは例えば、
- 震動
- 衝撃
- 荷重
- 海水
などのことです。
コンクリート養生期間に予想される振動、衝撃、荷重などの作用から保護するようにしてください。
また、材齢5日になるまでは海水に洗われないように注意しましょう。
そして、常圧蒸気養生とは高温度の水蒸気の中で行う促進養生のことで、大気圧下で行います。
さらに留意点についてまとめておきましたので参考にしてください。
常圧蒸気養生の留意点
- 型枠のまま蒸気養生室に入れ、養生室の温度を均等に上げる
- 練り混ぜ後、2~3時間以上経ってから蒸気養生を行う
- 養生室の温度は徐々に下げ、外気の温度と大差がないようになってから製品を取り出す
コンクリート養生の種類&養生期間まとめ(一覧表)
コンクリート養生の種類
| 湿潤養生
(湿潤に保つ) |
水中養生(標準養生) | コンクリートの強度試験用供試体のテストピースを20±3℃に保った水中、または湿度100%に近い湿潤状態で行う方法
空気中で養生するよりも温度変化が小さく、精度が高い |
|
| 湛水養生 | コンクリートの表面に数cmの水を張って養生する | ||
| 散水養生 | コンクリート表面に水を撒く(スプリンクラーなどを使用) | ||
| 湿布(養生マット、シート) | マットやシートなどで覆い、水分の蒸発を防ぐ | ||
| 湿砂 | 湿った砂でコンクリート表面を覆い、乾燥を防ぐ | ||
| 膜養生 | コンクリート表面に膜養生材を散布して被膜を形成し水分の蒸発を防ぐようにした養生 | 油脂系(溶剤型、乳剤型) | |
| 樹脂系(溶剤型、乳剤型) | |||
| 温度制御養生
(温度を制御する) |
マスコンクリート | 大塊状に施工される質量や体積の大きいコンクリート
厚さ80~100cm以上、下端が拘束された壁では厚さ50cm以上のコンクリート(コンクリート標準示方書) |
湛水、パイプクーリング |
| 寒中コンクリート | 日平均気温が4℃以下 | 断熱、給熱、蒸気、電熱など | |
| 暑中コンクリート | 日平均気温が25℃を超えるとき | 散水、日覆いなど | |
| 促進養生(工場製品) | コンクリートの凝結・硬化、強度発現を促進するためにコンクリートを加熱する養生方法 | 蒸気、給熱など | |
| 有害な作用に対し保護する養生 | 常圧蒸気養生 | 高温度の水蒸気の中で行う促進養生のことで、大気圧下で行う養生 | |
湿潤養生期間の標準日数
| 日平均気温 | 普通ポルトランドセメント | 混合セメントB種 | 早強ポルトランドセメント |
| 15℃以上 | 5日 | 7日 | 3日 |
| 10℃以上 | 7日 | 9日 | 4日 |
| 5℃以上 | 9日 | 12日 | 5日 |
以上です。
ありがとうございました。