

こんなお悩みを解決します。
また締固めについて、留意点や棒状バイブレータ(内部振動機)のコツなども解説します。
さらに土木の現場施工ではもちろんのこと、土木施工管理技士の記述試験にもよく出ますので要チェックです 😉
動画で確認したい方はこちらをどうぞ~
それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!
コンクリート締固めの留意点とは?棒状バイブレータ(内部振動機)のコツ
コンクリートの締固めの留意点はこちらです。
- コンクリートの締固めは棒状バイブレータ(内部振動機)を使うことを原則とする
- 棒状バイブレータ(内部振動機)は鉛直に挿入し、挿入間隔は、一般的に50cm以下とする
- 棒状バイブレータ(内部振動機)はコンクリート下層に10cm程度挿入する
- うすい壁などの内部振動機が使えない場所は、型枠振動機をつかう
- 締固めの時間目安は、一カ所あたり5秒~15秒とする
- 棒状バイブレータ(内部振動機)を引き抜くときは、後に穴が残らないようにゆっくりと引き抜く
- 再振動するときは、コンクリートの締固めができる範囲でできるだけおそい時期にする
土木施工管理技士の記述試験などでも、このまま書けばOKです。
しっかりチェックしておきましょう。

締固め留意点➀コンクリートの締固めは棒状バイブレータ(内部振動機)を使う
内部振動機とは、コンクリートが固まる前の状態でつかう棒状の振動機のことです。
棒状バイブレータともよばれ、生コンクリートの中に入れて使います。
基本的に、コンクリートの締固めには内部振動機を使うと知っていればOKです。
締固め留意点②棒状バイブレータ(内部振動機)は鉛直に挿入し、挿入間隔は、一般的に50cm以下

内部振動機をコンクリートに挿入するときは、鉛直になるようにしてください。
また内部振動機を使う間隔は、50cm以下になるように挿入してください。
締固め留意点③棒状バイブレータ(内部振動機)は下層に10cm程度挿入

2層以上のコンクリートに締固めをする場合は、内部振動機がコンクリート下層に10cm程度挿入するようにしてください。
内部振動機が下層に入っていないと、振動がうまく伝わらずコンクリートの締固めができません。
締固め留意点④うすい壁などの内部振動機が使えない場所について
コンクリートの締固めにおいて、うすい壁などの場所には内部振動機が使えない場合があります。
そんなときは、型枠振動機を使って外部から振動を与えて締固めます。
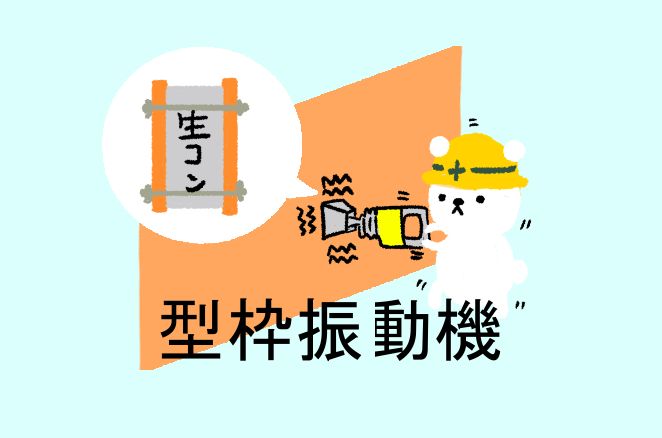
締固め留意点⑤締固めの時間目安
コンクリート標準示方書〔施工編)の記載されている基準です。
振動時間はどぼ施工管理技士の試験でもよくきかれますのでしっかり覚えておきましょう。
コンクリート締固めの時間目安は1カ所あたり5秒~15秒です。
締固め留意点⑥棒状バイブレータ(内部振動機)を引き抜くときのコツ
内部振動機をすばやく引き抜いてしまうと、コンクリートに穴が残ってしまい、コンクリート内部の骨材が均等になりません。
だから内部振動機を引き抜くときは、コンクリートの様子をみながらゆっくり引き抜くようにしてください。
締固め留意点⑦再振動する時期について
コンクリートの材料分離がみられてたり、ひびわれをしてしまったりしたときは、コンクリートを再振動させて締固めなければなりません。
再振動するときには、コンクリートの締固めができる範囲でおそい時期にしてください。
時間の目安としては、150分程度です。
この150分という時間は、コンクリートの許容うち重ね時間を参考にしています。
コンクリート打ち込みについてはまた別記事で併せてご確認下さい。
締固め留意点⑧コンクリート締固め後の仕上がり面について
コンクリート締固めにおける仕上がり面のポイントはこちらです。
コンクリート仕上がり面のポイント
- 締固めがおわってならしたコンクリートの表面は、しみでた水がなくなるか、表面の水をとりのぞくまで仕上げてはならない
- 仕上げ作業時、コンクリートが固まりはじめるまでの間に発生したひびわれは、タンピングまたは再振動によって修復しなければならない
- コンクリート表面をなめらかにしなければならない場合は、金ごてで強い力をくわえてコンクリート表面を仕上げること
締固めがおわってならしたコンクリートの表面について
コンクリートを締固めたあと、コンクリートの表面には不要となった水が出てきます。
この水を【ブリーディング水】とも呼びます。
コンクリート表面を仕上げるときには、しみ出た水や表面の水を取り除いてから仕上げるようにしてください。
仕上げ作業時、コンクリートが固まりはじめるまでの間に発生したひびわれについて

仕上げ作業のときにひびわれが発生してしまった場合は、タンピングや再振動をしてひびわれ部分をなくさなければなりません。
タンピングとは、コンクリートをタンパーと呼ばれる機械でたたいて、締め固めていく作業のことです。
タンピングをすることによって、表面の強度が強くなりひびわれにくくなります。
ひびわれ部分を残したまま、コンクリートが固まってしまうと強度が下がってしまいます。
コンクリート締固め後は、ひび割れがないか自分の目でみて確認するようにしましょう。
コンクリート表面をなめらかにする場合は金ごてを使用
コンクリートの表面をなめらかにする場合は金ごて(かなごて)を使います。
金ごてを使うときには作業が可能な範囲で、できるだけおそい時期にやりましょう。
ブリーディングが終わってコンクリートが落ち着くのは、1~2時間程度と言われています。
この時間を目安にブリーディング状況を確認して仕上げをおこなってください。
またこて仕上げを入念にやりすぎると、表面にペーストが集まりすぎて収縮ひび割れの原因となるので注意しましょう。
コンクリート締固めの留意点とは?棒状バイブレータ(内部振動機)のコツや仕上げまとめ
今回は以上です。
参考になればうれしいです。
ありがとうございました。
この記事を書いている人

- 元地方公務員の土木ブロガー💻
- 国立大学★土木工学科卒業(学士)
- 1級土木施工管理技士、玉掛、危険物取扱者乙4などの資格を取得しています。
- 県庁の公務員土木職で7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 現在は、土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにブログやYouTubeでさまざまな情報発信をしています。



