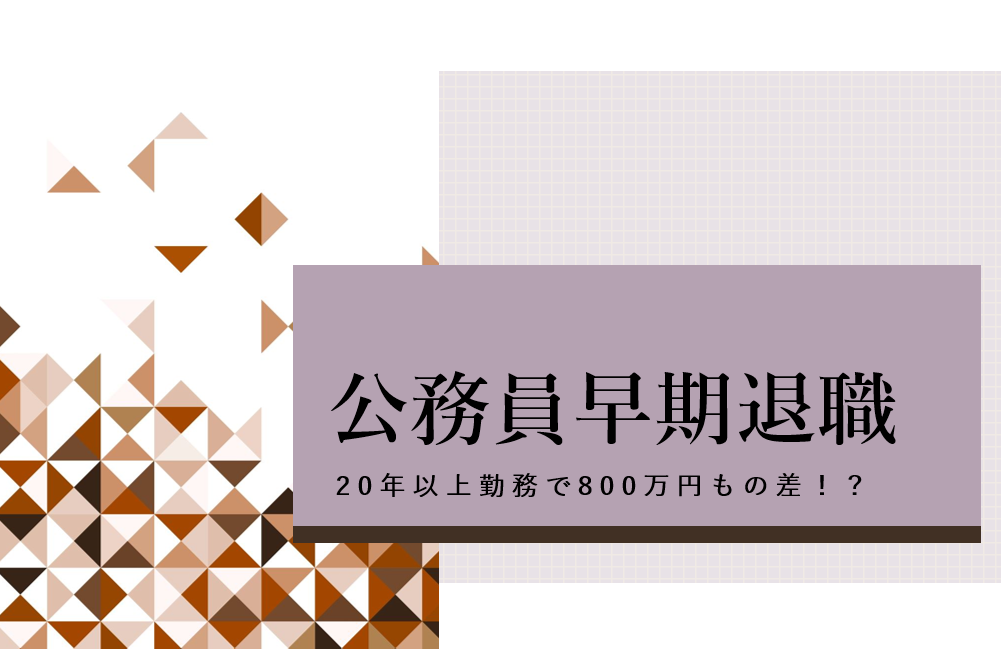こんにちは、元公務員のみんです。
今回は公務員の早期退職に関する退職金について解説していきます。
公務員の早期退職者募集制度は、2013年11月1日から適用され、早期退職をする方は年々増加傾向にあります。
しかし、まだまだ早期退職に対する不安や疑問はたくさんあるようです。

こんなお悩みを解決します。
この記事を書いている人

- 元地方公務員ブロガー
- 某県庁の公務員土木職で7年間勤めた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 現在は、土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事などをメインにブログでさまざまな情報発信をしています。
それではさっそく参りましょう。ラインナップはこちら!
公務員の早期退職者募集制度とは?(退職金の割増し制度あり)
公務員の早期退職者募集制度とは、会社側が早期退職者の募集人数や年齢等の応募条件を定めて、定年前に退職する意思をもつ職員を募集する制度のことです。
早期退職したい人~手あげて~!

といった感じで本人が応募します。
今までは、会社側からの労働契約解除の申し入れる勧奨退職(通称:肩たたき)や自己都合退職しかありませんでした。
また、内閣人事局のHPでは、早期退職者制度についての目的を以下のように述べています。
職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を目的として、45歳以上(定年が60歳の場合)の職員を対象に、透明性の確保された早期退職募集制度を創設。
引用:内閣人事局国家公務員制度https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/
要するに、人員削減です。
管理職になるような年代が増えてしまい、人員のバランスが取れなくなっています。
また、仕事も機械やAIがどんどん参入してくる時代…。
パソコンがなかった世代からすれば、目まぐるしすぎる時代の変化でしょう。
公務員の早期退職者制度(退職金の割増し)が適用されるのはどんな人?
 早期退職者制度が適用されるのはこんな人です。
早期退職者制度が適用されるのはこんな人です。
- 勤続年数20年以上
- 定年前15年以内
2022年度から、国家公務員の定年は60歳から65歳へと延びるでしょう。
これに準じて、地方公務員も同じく定年は65歳になるはずです。
- 定年60歳なら45歳
- 定年65歳なら50歳
の適用となり、さらに勤続年数が20年以上という条件も加わります。
勤続年数とは、職員として働いた在職期間のことです。
自治体にもよりますが、休職、停職、育児休業などの期間は、期間の1/2が除算され、育児休業で、子供が1歳になるまでの期間は1/3が除算されます。
| 具体例 | 勤続年数 |
| 例1)1年間の休職の場合 |
勤続年数は約120日 (1ヵ月20日×12か月=240日÷2=120日) |
| 例2)1年間の育児休業の場合 |
勤続年数としては約80日 (1ヵ月20日×12か月=240日÷3=80日) |
これらの条件をクリアすると、退職金割増し制度が適用されます。
公務員の退職金★早期退職と自己都合退職での退職金には800万円以上の差が!

早期退職制度では、早期退職者に対する退職金手当が多くもらえる割増し制度があります。
割増しは、定年までの残りの年数1年あたり3%の割増が適用されますよ。
45歳で早期退職するとなると、15年(定年までの年数)×3%=45%の割増しとなるわけです。
例として、45歳(勤続年数23年)で早期退職したとすると、定年退職と同じく扱われるため、退職金の支給率は月額給料×31月分にもなります。
さらにこの金額に対し、最大で15年×3%=45%が加算されるので、給与月額を40万円とすると、
40万円×31月×1.45(45%UP)=約1,800万円にもなります。
自主退職の場合は、逆に「勤続20年以上かつ15年以内の退職」の条件を満たさない必要があるので、
先の例と一番近い金額で比較しようとすれば、
大卒22歳で入庁し、44歳(勤続年数満22年)で自己都合退職した場合の退職金支給月数は24.6月となります。
40万円×24.6月=約984万円
| 具体例 | 退職金 |
| 大卒22歳で入庁45歳(勤続年数満23年)で早期退職募集制度を利用した場合 | 約1,800万円 |
| 大卒22歳で入庁44歳(勤続年数満22年)で自己都合退職した場合 | 約984万円 |
差額 1,800万円-984万円=816万円
つまり、たった1年の差だけで、約816万円も退職金がちがうのです!
800万円多くもらうか、少しでも早く労働のストレスから解放されるか… むずかしいところですが、退職についてはよく考えたうえで検討してみてください。
また、公務員退職金の支給率については、別の記事でくわしく書いていますのでそちらをご覧ください。
ちなみに退職金には税金(所得税+住民税)がかかるのでご注意ください。
公務員の早期退職における退職金まとめ
<strong>公務員早期退職金の割増まとめ</strong>
- 公務員の早期退職者募集制度とは、会社側が早期退職者の募集人数や年齢等の応募条件を定めて、定年前に退職する意思をもつ職員を募集する制度
- 早期退職者制度(退職金の割増)が適用されるのは、勤続年数20年で定年まで15年以内の人
- 割増で早期退職と自己都合退職での退職金には800万円以上の差!
- 退職金には税金(所得税+住民税)がかかるのでご注意を!
今回は以上です。
ありがとうございました。